中期の傑作
印象的な第1楽章の序奏から最終楽章の感動的なコーダまで、聞きどころは多い。なかでも第4楽章アダージェットは、官能的で悲しく美しい調べに魅了される名曲であり、ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画『ヴェニスに死す』でも使われた。マーラーの直弟子にあたるクレンペラーは、これを「まるでムード音楽のようだ」と嫌っていたため、マーラーの5番そのものを指揮しなかったという。
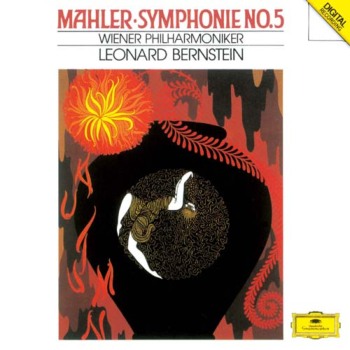
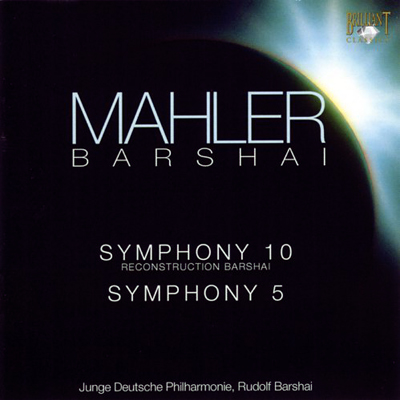
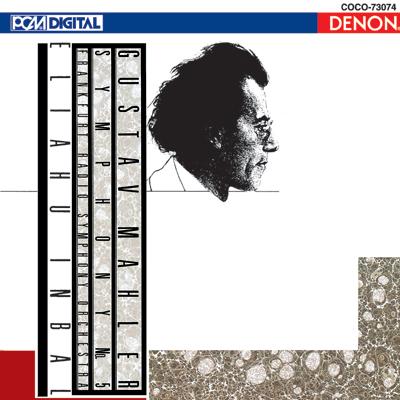 第一のおすすめとして、インバル/フランクフルト放送響の演奏(コロムビア)を推したい。単に録音が優れているというだけでなく、演奏の完成度が極めて高いからである。ホルンをはじめ、金管群は決して音を濁らすことも音程を外すこともないし、弦に至ってはひとつの楽器のようだ。一糸の乱れもない。
第一のおすすめとして、インバル/フランクフルト放送響の演奏(コロムビア)を推したい。単に録音が優れているというだけでなく、演奏の完成度が極めて高いからである。ホルンをはじめ、金管群は決して音を濁らすことも音程を外すこともないし、弦に至ってはひとつの楽器のようだ。一糸の乱れもない。この弦の素晴らしさは4楽章で惜しみなく発揮されており、ゆったりとしたテンポを採っていた当時のインバルの指揮のもとに、息が止まるような演奏をしてみせている(アダージェットにおいて11分半をかける演奏は、他の指揮者と比べてもかなり遅い部類である。余談ながら、近年インバルがチェコ・フィルと再録した演奏では、速めのテンポを採っている。こちらも文句なく上手い)。
また、この演奏は販売元であるコロムビアの自信作らしく、音質の改善を図るなどして繰り返し再販されているので、手に入れやすいこともおすすめする理由の一つである。どんなに良い演奏であっても、入手して聴くことが難しいのであれば、推薦する意義に乏しいからである。
インバルに続くものといえば、バルシャイ/ユンゲ・ドイチェ管(BRILLIANT)、ハイティンク/コンセルトヘボウ管(PHILIPS ※クリスマスマチネー集)、エッシェンバッハ/北ドイツ放送響(En Larmes)、バーンスタイン/ウィーン・フィル(プロムスでのライブ。GNP等)が挙げられる。引き締まった造形のバルシャイ、熱気に充たされたハイティンクのクリスマス・マチネー公演、ただひたすら暗いエッシェンバッハ、壮絶なバンスタと、いずれも凡百の演奏とは次元が違う。
残念ながら、エッシェンバッハ、バンスタについてはいずれも非正規盤のCD-Rなので、街のCD販売店やAmazon等の大手通販サイトでも購入できないのが難点である。ただし、ヤフオクや中古CD店ではお目にかかることも多いので、購入したい方はこれらを利用されるとよい。なお、CD-Rは、ある日突然読み込みできなくなったりすることがあるから、そのあたりはご承知のうえで入手されたい。
ガリー・ベルティーニ/ケルン放送交響楽団
11'16, 14'35,17'12,10'05,14'25 [1990年]
(EMI)
★★
ガリー・ベルティーニ/ウィーン交響楽団
12'38,15'00,17'12,11'29,13'47 [1983年4月12日]
(Weitblick)
★★
クリストフ・エッシェンバッハ/北ドイツ放送交響楽団
13'24,15'44,18'18,12'07,14'34 [2001年]
(En Larmes)
★★★
ロジャー・ノリントン/シュトゥットガルト放送交響楽団
11'33,14'26,17'19,08'54,15'23 [2006年]
ノリントンが清新なアプローチで世に問うマーラーの5番。マーラーの時代にはヴィブラートが一般的でなかったということを根拠に、ヴィブラートを排しての演奏となっている。
楽器配置も考慮され、ブックレットによれば、ヴァイオリンは両翼に、コントラバスは木管の後ろに、ホルンは左側、トランペット、トロンボーン、チューバは右側へ配置されているようだ。
演奏の方は、やはりすっきりとした印象。弦楽器とハープのみのアダージェットは、ノン・ヴィブラートの効果により陶酔的ではないが、悪くない。バロック時代の弦楽を聴くようで、むしろ斬新。
(hänssler)
★★
ベルナルト・ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
12'52,14'14,19'05,11'06,15'38 [1986年]
Dutch Masters。1986年のクリスマス・マチネーにおけるライブ。
(PHILIPS)
★★★
ベルナルト・ハイティンク/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
13'33,15'47,19'17,13'55,15'54 [1988年]
カラヤンに鍛えられたベルリンフィルの上手さに脱帽する。ハイティンクはまったくもって侮れない。
全体的にゆったりと聴かせる。第2、3楽章はその効果もあって、本当に素晴らしい聴きごたえ。下のフランス国立管が「渋上手さ」なら、こちらは「ドイツ的重厚長大名人芸」とでも言おうか。このスローテンポをこの密度で弾けるのはベルリンフィルだからこそだろう。
アダージェットも14分に迫ろうかという長さ。しみじみとしている。
(PHILIPS)
★★
ベルナルト・ハイティンク/フランス国立管弦楽団
14'09,15'26,21'14,10'26,16'54 [2004年]
ハイティンクが好きだという人をあまり知らない。しかし、彼の手堅い仕事は評価すべきだと思う。特に、マーラーの3番は、ACOのクリスマスマチネ盤、ベルリン・フィル盤、そしてシカゴ響盤のいずれも素晴らしいの一言である。
この表現は陳腐であるが、哀愁のある演奏だ。第2楽章・第3楽章などは、フランス映画のバックに流れていても不思議ではない。フランス国立管の渋い音に酔いしれる。
(Naive)
★★★
ミヒャエル・ギーレン/バーデン=バーデン・フライブルク 南西ドイツ放送交響楽団
13'10,15'08,16'25,08'30,15'37 [2003年12月9-10日]
(hänssler)
★★
エリアフ・インバル/フランクフルト放送交響楽団
13'31,14'04,18'46,11'34,14'27 [1986年]
マーラー5番の頂点だと思う。細部まで明瞭でありながら、それでいて全体が細部に拘束されることのない、インバルの響き。アダージェットの静かで豊かなハーモニーは空前絶後。爆演のみが心を打つわけではない、という至極当然ながらも、忘れがちな事実を理解させてくれる。これはインバルの真骨頂である。もし、一枚だけ挙げろといわれれば、私はこれを推す。
この録音はDENONの自信作のようで、多くのバリエーションが存在する。
私の手元にあるものだけでも、1.通常版、2.ゴールドディスク版(3000枚限定)、3.ワンポイント・マイク録音版、4.HQCD版(ワンポイント・マイク録音)の4種がある。
(コロムビア)
★★★
クラウス・テンシュテット/ニューヨーク・フィルハーモニック
(NYP)
★★
クラウス・テンシュテット/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
13'47,15'12,18'09,11'55,16'15
(EMI旧録音)
★★
クラウス・テンシュテット/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
13'38,15'25,18'05,11'21,14'52 [1988年]
(EMI新録音)
★★
クラウス・テンシュテット/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
14'45,15'42,18'17,12'00,15'30 [1984年4月13日]
(KING)
★★
クラウス・テンシュテット/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
14'37,15'48,18'34,12'14,14'48 [1990年]
EMI盤は伴侶というべきロンドン・フィルとの演奏だったのに対し、これはコンセルトヘボウ管とのライブ。世界屈指の名オケと、指揮者として最晩年を迎えていたテンシュテットとの白熱の演奏である。
第1、2、3楽章と徐々にオケも指揮者も乗ってくる。ちょっとしたミスなど、全く意に介することはない。アダージェットにきていよいよ「入神」状態。最後の一音は極端に音量を落とすが、緊張感は落ちることなく、むしろ極度の高まりを見せる。最終楽章も大胆なデュナーミクで聴き手を圧倒する。
テンシュテットは1998年に亡くなったが、死の数年前には活動をやめていた。早すぎる死を、私はいまさらながら惜しむ。
- 2011/7/17追記…いよいよ、ロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団アンソロジー第6集1990-2000(RCOLive)に収録されて正規発売される。
- 2011/7/23追記…上述のアンソロジー集を入手。000classics盤と比べ録音が明瞭になっていることと、ノイズ・騒音が無くなっていることが確認できた。とくに、静謐な4楽章でサーノイズを気にしなくてよくなったことはうれしい限りである。ただし、録音としては000classics盤も健闘していたことが分かる。
(RCO LIVE/000 CLASSICS)
★★★
レイフ・セーゲルスタム/デンマーク国立放送交響楽団
13'09,14'33,19'33,11'47,16'11 [1994年]
(CHANDOS)
★★
ゲオルグ・ショルティ/シカゴ交響楽団
11'54,13'49,16'39,09'51,13'39 [1970年]
(DECCA1回目)
★★
ゲオルグ・ショルティ/シカゴ交響楽団
12'35,14'30,16'58,09'42,14'53 [1990年]
以前はショルティの演奏が苦手だった。確かによく鳴るし、上手い。確かに上手いのだが、ただそれだけの演奏ではないかと思っていた。しかし、年齢を重ねてみると、ショルティがいかに丁寧な音作りに苦心していたかが理解できる。
この演奏は、ショルティのマーラーの演奏の中でも特に良い部類に属する。
(DECCA2回目)
★★
ゲオルグ・ショルティ/チューリヒ=トーンハレ管弦楽団
12'24,14'44,16'42,09'58,14'49 [1997年7月]
(DECCA3回目)
★★
ロリン・マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
14'01,15'00,17'34,10'29,15'12 [1982年]
(SONY)
★★
ロリン・マゼール/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
14'48,15'22,18'12,12'22,15'15 [1991年12月1日]
(PANDORA's BOX)
★★
ロリン・マゼール/バイエルン放送交響楽団
13'21,14'54,17'53,11'18,14'51 [2002年]
バイエルン時代のマゼールは今までにも増して奇妙な境地に入ったらしく、快演かつ怪演を連発していた。
マーラーでは9番が正規盤DVDとして出ているのだが、それ以外では海賊盤でしか接することができないのが残念。この5番も海賊盤。
バイエルンを去った後、マゼールはNYPの指揮者になっていたはずだが、こちらとのCDはあまり出ていないのが現状である。ただし、Amazon等のMP3ストアでは、NYPとのマーラーツィクルスが購入できる。
(En Larmes)
★★
レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック
12:25,14:15,17:36,11:00,13:44
バーンスタインの旧録音。ニューヨークフィルの明るく硬めの響きが、晩年におけるウィーンフィルとの演奏に慣れた耳には新鮮。オケの機動性も高く、陶酔しすぎないすっきりとした演奏で良い。
晩年の演奏だけがバーンスタインの魅力ではないことを教えてくれる。
(CBS)
★★
レナード・バーンスタイン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
14:34,15:05,19:07,11:12,15:00 [1987年9月6-8日]
グラモフォンの正規盤。フランクフルトでのライブ録音である。
第1、2、3楽章はなかなかの演奏。まとまりもよく聴きやすい。特に第2楽章は秀逸。ドロドロの暗黒。アダージェットはかなりの出来。恐怖さえ感じる。
下の海賊盤よりもノイズがない分だけ弱音が闇のように恐ろしい。
(DG)
★★★
レナード・バーンスタイン/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
14:07,14:30,18:28,11:16,15:03 [1987年9月10日]
ロンドンのプロムスライブ。
上のフランクフルトでのライブとは数日しか離れていないので、演奏のスタンスも基本的に変わらないものの、白熱の度合いではこちらが上。
特に第3楽章からは、ノリが一段と増している。聴いているこちらもどんどん引き込まれる「魔演」。
演奏全体の精度では先のDG盤が上だが、ライブ感という点ではこの盤に軍配が上がる。音のバランスも良い。
世の中には、どういうわけか、非正規盤を正規盤よりむやみやたらに高く評価する人たちがいるが、それは自己陶酔的錯覚にすぎない。無論、正規盤をしのぐ演奏もあるが、海賊盤のほうが常に名演ということはありえない。
(First classics)
★★★
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
13'05,15'12,18'10,11'53,15'25 [1973年]
(DG)
★★
ユーリ・テミルカーノフ/サンクトペテルブルク・フィルハーモニー管弦楽団
13'29,14'12,18'03,10'24,14'41 [2003年9月20,22日]
(Water Lily Acoustics)
★
ファビオ・ルイージ/中部ドイツ=ライプツィヒ放送交響楽団
12'44,15'37,19'30,12'35,15'31 [1997年]
1959年生まれのファビオ・ルイージ。しっとりと丁寧で、かつ、きっちりと音楽を盛りあげる。一番のポイントは弱音の処理がとても上手いこと。部分的には不安定なところもあるものの、他の人の指揮では思いもよらぬところに音楽の美しさを発見させてくれる。
最近では珍しいタイプの指揮者。
(VKJK)
★★
ズビン・メータ/ニューヨーク・フィルハーモニック
11'38,14'05,18'00,10'50,14'54 [1989年9月]
(Apex)
★★
ピエール・ブーレーズ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
12'52,15'02,18'12,10'59,15'12 [1996年]
(DG)
★★
アンドレ・プレヴィン/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
13'25,15'05,18'21,11'36,16'51
(RPO)
★
クラウディオ・アバド/シカゴ交響楽団
12'54,15'17,17'40,11'55,14'40
アバドはこの盤が一番いいと思う。音楽が、そしてアバドが生き生きとしている。最終楽章は響きの厚さとオケの正確さに、ただただ圧倒。ベルリン盤は残念ながらこのシカゴ盤をしのぐまでには至っていない。この曲の良さを私に初めて教えてくれたのは、このアバド・シカゴ盤だった。
(DG)
★★★
クラウディオ・アバド/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
12'36,14'46,17'27,08'58,15'42 [1993年]
(DG)
★★
クラウディオ・アバド/ルツェルン祝祭管弦楽団
12'42,14'43,16'56,08'33,16'26 [2004年]
ルツェルン音楽祭でのライブDVDである。以前は輸入盤しかなかったが、いまは国内盤も出ている。
このルツェルン音楽祭を舞台にするルツェルン祝祭管は、世界でソロとして活躍する一級の奏者を集めて編成されるオーケストラ。
確かに上手い。音も出ている。が、ソロで活躍するプレーヤーが主体だからなのか、音が直線的というか、楽器の音が溶けあっていないように聴こえる。音が硬い。むろん録音のせいということもあるが。それを抜きにしても、アバドはここでもシカゴ盤ほどの精彩さはない。
(EURO ARTS)
★★
ジョルジュ・プレートル/ウィーン交響楽団
13'32,15'24,18'02,11'21,14'47 [1991年5月19日]
(Weitblick)
★★
ミヒャエル・スダーン/ザールブリュッケン放送交響楽団
11'48,13'17,16'18,11'25,15'08 [1997年9月12日]
(PERCPRO)
★
ギュンター・ヘルビヒ/ベルリン交響楽団
11'19,13'22,17'58,09'58,14'27 [1982年]
(edel)
★
アントニ・ヴィト/ポーランド国立放送交響楽団
12'50,14'56,19'33,12'03,14'53 [1990年8月16-18日]
(NAXOS)
★★
リカルド・シャイー/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
12'51,15'11,17'55,10'20,15'24
(DECCA)
★★
ヴァツラフ・ノイマン/チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
11'23,13'30,18'58,10'28,16'07 [1993年]
(EMERGO)
★★
アヴィ・オストロフスキー/ベルギー=ブリュッセル放送管弦楽団
13'02,15'52,18'34,11'20,15'02 [1994年]
(DISCOVER)
★
ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団
12'08,13'42,17'26,10'28,15'09 [1985年]
シノーポリは良くわからない指揮者である。細かくいろいろなことをやりたいのか、あるいは曲を大づかみにしてコントラストで勝負をかけたいのか、わからない演奏が多い。結局、消化不良感を聴き手に与えてしまう。
しかし、この演奏は良い。いまいちぱっとしないフィルハーモニア管もここでは一定のテンションをキープしている。
ところどころ編集の痕跡が聴こえるのは気のせいか。
(DG)
★★
ジュゼッペ・シノーポリ/シュターツカペレ・ドレスデン
13'26,14'22,17'54,11'27,14'28 [1999年11月5日]
海賊盤であるうえ、ネット上にも情報がほとんどないので、シノーポリの指揮かどうかは断言できない。しかし、ほかの指揮者はやらないようなことをいろいろやっており、シノーポリの指揮で合っているように思われる。弦楽器が繊細の極みの美音を奏でているのに比べ、トランペット、ホルンが全体的に不安定。クレジットどおりSKDだとすると、ペーター・ダムが乗っていてもおかしくないが、なんとも調子が悪い。また、この曲の聴きどころであるアダージェットのラストで盛大に聴衆の咳が入っているのも残念。このあたりが正規発売されない理由ではないか。
海賊盤を扱っていたHarvest Classicsはすでに業務を止めているので、今後入手しにくいかもしれない。
(Harvest Classics)
★★★
ルドルフ・バルシャイ/ユンゲ・ドイチェ管弦楽団
11'53,14'26,18'29,08'17,16'18 [1999年]
インバル、バーンスタイン、テンシュテットと並ぶ演奏が、このバルシャイ盤。全体的にすっきりとしたスタイルで聴かせる。とくにアダージェットは粘ることなく早めのテンポで進んでいくが、最後の下降動機のフレージングが独特で、バルシャイのセンスの良さを堪能できる。
残響を若干多めにしてあるせいか、硬さが抑えられていて、とても心地よく聴ける。
入門のひとつとしてもお薦め。
(BRILLIANT)
★★★
エド・デ・ワールト/オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団
13'53,15'27,18'47,10'01,15'44 [1992年]
(RCA)
★★
ラファエル・クーベリック/バイエルン放送交響楽団
11'35,13'52,17'23,09'44,15'29 [1971年1月]
ミュンヘンでの演奏。
世界にその名をとどろかせる名オーケストラ・バイエルン放送響とクーベリックとのマラ5。
とにかく簡潔。簡潔過ぎの一歩手前といってもいい。だが、要点をきっちりとおさえた佳演。全体的に早めのテンポで、妙なうねりや伸びをつけない分、音の構造がわかりやすい。
バイエルンが本当にいい仕事。クーベリックの指揮の確かさを実感できる。
(DG)
★★
ラファエル・クーベリック/バイエルン放送交響楽団
12'40,14'54,17'55,10'27,15'00 [1981年]
71年の演奏より濃い目の演奏。クーベリックも心境の変化があったのだろうか。DGの録音のときは「簡潔にすぎる」と思われるところも、きっちりと表情をつけたものになって、感情移入しやすいといえる。特にアダージェット。
もちろん、これは好みの問題であって、「簡潔な方がいい」という人もいようし、それを否定する気は全くない。
(First classics)
★★
ラファエル・クーベリック/バイエルン放送交響楽団
11'35,13'52,17'23,09'44,15'29 [1971年1月]
(DG)
★★
マリス・ヤンソンス/バイエルン放送交響楽団
12'52,15'25,18'35,10'25,15'00
友人にヤンソンスのファンがいる。正直、私は腑に落ちないでいた。
しかし、このバイエルンとの演奏を聴き、ようやくヤンソンスが「ただもの」でないことを知ったのであった。
(En Larmes)
★★
エフゲニー・スヴェトラーノフ/ロシア国立交響楽団
14'40,14'42,19'26,09'55,14'17 [1995年]
(harmonia mundi)
★★
ユッカ・ペッカ・サラステ/フィンランド放送交響楽団
11'41,13'44,18'43,09'21,14'36
(EMI Virgin)
★
ジェイムス・コンロン/ケルン・フィルハーモニー=ギュルツェニヒ管弦楽団
12'44,14'12,18'29,10'30,15'00 [1994年]
コンロンは1950年生まれの指揮者。
中庸を極めに極めた粋な演奏である。複雑なことを考える必要もなく、頭の中に音楽が入ってくるよう。マーラーの交響曲でこういう演奏ができる人も少ないと思われる。
(EMI)
★★★
ジョン・バルビローリ/ニューフィルハーモニア管弦楽団
13'40,15'09,17'59,09'51,17'23 [1969年]
(EMI)
★★
セミヨン・ビシュコフ/ケルンWDR交響楽団
13'51,15'53,18'05,09'32,16'05 [2004年]
演奏自体はまずまずであるが、いかんせん録音が悪すぎる。大きな音はひずみがち。
(En Larmes)
★
ダニエレ・ガッティ/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
13'01,14'08,17'18,10'12,14'56 [1997年11月15-17日]
(RCA BMG)
★
オトマール・スウィトナー/シュターツカペレ=ベルリン
10'51,13'00,16'01,10'08,13'54 [1984年]
(Schallpratten)
★★
エーリヒ・ラインスドルフ/ボストン交響楽団
11'32,12'59,17'23,08'30,14'05
(BMG)
★
サイモン・ラトル/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
13'03,14'28,16'59,09'32,15'02 [2002年]
(EMI)
★★
ジェイムズ・レヴァイン/フィラデルフィア管弦楽団
12'56,14'52,17'35,12'03,14'54 [1977年]
(RCA)
★★
クリストフ・フォン・ドホナーニ/クリーヴランド管弦楽団
12'09,12'54,15'32,10'19,14'11 [1988年7月]
(DECCA)
★
キリル・コンドラシン/ソヴィエト連邦国立交響楽団
11'03,12'44,16'57,08'10,13'50 [1974年]
(Melodiya)
★★
ガブリエル・フェルツ/シュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団
12'47,15'11,17'21,12'29,13'54 [2009年1月13日]
(Dreyer Gaido)
★
ヴァレリー・ゲルギエフ/ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団
13'17,14'44,18'16,10'17,15'41 [2001年1月2日]
(LIVE SUPREME)
★
ハロルド・ファーバーマン/ロンドン交響楽団
14'11,15'34,19'54,12'03,16'43 [1980年]
(VOX)
★
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー/モスクワ放送交響楽団
11'44,13'07,17'06,09'04,14'08 [1973年12月23日]
これは全くお勧めできない。ステレオ録音との触れこみであるが、ほとんどステレオ感がない。音自体も貧弱で、ロジェストヴェンスキーの凄さが微塵も感じられない。
★
ネーメ・ヤルヴィ/スコティッシュ・ナショナル管弦楽団
13'04,14'08,18'11,10'46,14'07 [1989年10月23-24日]
(CHANDOS)
★★
ヤープ・ファン・ズヴェーデン/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
13'00,14'16,17'33,09'56,14'45 [2008年1月16日]
(LPO)
★★
ズデニェク・マーツァル/プラハ交響楽団
11'29,14'39,19'11,10'49,14'50 [2001年2月13日]
(Music Vars)
★★